久々に週明け早々にブログを更新します。
土曜日は1日仕事のため練習に参加できませんでしたが、昨日の日曜日は午前、午後とも参加することができました。
でもよりによってそんな時に天気は崩れ、気温も下がる中で降り続いた雨によって体の芯から冷え切ってしまいました。
こんな日は本当に練習すること自体、部員らにも頭が下がる思いですが、それでも心を鬼にして、これから残り半年となった今季に向けて、あれやこれやと伝えた1日でした。
週中、淡路からはいつものように一週間のモーションとメニューが発信されました。
私はこれに対して、「この練習の意図と目的は何か?」と投げかけたのですが、これについて話し合いを持ちたいとのことで午前の練習後に四人で話し合いの機会をもちました。
その中で、今、彼らが考えているレース目標やそれに向けた練習ペースを聞きました。
自分たちで考え、納得して行っていくことは大事です。
でも勝つために今必要なことを私は自分の思いとして率直に伝えました。
その内容が私のエゴか、はたまた腹に落ちて納得できるか、それは正直わかりません。
でもインカレでメダルを獲りたいと決意してから半年が過ぎ、このままではいけないという思いが私の中にはずっとありました。(それはきっと彼らも同様だと思っています)
思い返せば、自身もインカレで結果を出そうと心に決め、本当の意味で覚悟を決めたのは6月も過ぎた頃でしたから、そう考えるとそれより早い時期でもあるのです。
そんな私が彼らに投げかけたことをそのまま伝えます。
インカレでメダルを獲るために必要なこととして、エルゴ記録を一つの指標としています。
これは記録を出すことで、その自信が力に変わり、心身ともに成長していくために必要なことだからです。
そしてそのスコアは夏の練習中の間に記録すればいいものではなく、この春のうちにこそ達成すべきと思っています。(今までのシーズンでは夏にピークをもっていくことが通常でした)
なぜなら早い段階でその自信を植え付けさせ、その後の練習に励むことの方が、心身ともに余裕をもって行えるからです。
エルゴスコアには、これでなら勝てるという指標はありません。ただ、少なくとも目安となるタイムはあります。
例えば、目標とする入試においてE判定で勉強し続けることと、C判定を取って本番に向かうことではどちらに気持ちに余裕があるでしょうか。
手ごたえがなく、本番に挑むことは目標への気持ちそのものが揺らいでしまう可能性すらあるからです。
また、それとは別に練習内容というものに意味をもつことの大切さを改めて伝えました。
改めてというより、今まで実はこうした考えをあまり伝えていなかったのは、ある程度の練習方法を与えた後、あとは自分たちで考えることを優先させ、納得いく行動をしてほしかったからです。
でもこの半年間の努力ではまだ結果に結びついていないという現実。そしてこのまま続けていても先がない現実を知るからこそ、今日はあえて自身の考えを伝えました。
青山学院大学ボート部はここ数年、インカレの出場記録を出すことはある程度、達成できる状況に至ります。(これだけでも皆、すごいことだと当時の自身の現役時代を知る私はそう思っています)
ただし、これが今の練習法の一つ、ベースラインでもあるのですが、その先は彼らにとっても未知の領域なのです。
この今の練習法は言わば、競技を始めてから最高でも80点までは取れるという方法です。
でもこの80点というのは実は努力すれば誰でも到達できるもので、これだけでは我々が掲げる目標に達しないのです。
試験に例えても同じだと思います。その先の90点や100点を取るために必要なこと、これこそが自ら考えて行動することが必要です。
では、果たしてそれは何だと思いますか?
私自身は、そこから先は弛まぬ努力と総量だと思っています。いわゆる血と汗の結晶というやつです。
一種の天才という人であれば、これをいとも簡単にクリアしてしまうのかもしれませんが、大抵の人は自分なりに残りの点数を取るために必要なことを考えて、それを実行するのだと思います。
私が教えるボートでもその通りです。
80点までは取れるようにしていながらもここから先、さらなる高みを目指すためには今までの練習法でやっていても変わらないことに気づいてほしかったのです。
そして私たちは普段の練習で何をすればいいかというヒントも実は得ているのだということを伝えました。
そのことを自覚し、自らに課し、勝負できるだけの力を身につけなければいけないのです。
私たちボート部は少数がゆえに自ら考えて実行できる組織、環境です。
これが数十名いたらチームとしての行動、メニューを問われるので自分の意図には反したかたちで、練習内容を与えられるかもしれません。
でも自由度が高い当部では自ら考えて実行し、それがたとえ失敗であっても、それを生かし、すぐに軌道修正し、変えていけるという強みがあります。
むしろそういう環境だからこそ自らの考えや行動で未来を切り拓いていけるのです。
強いチームというのは誰かが決めたお手本、教科書がすでにあり、嫌でもライバルがいることでの競争意識が己を強くできる要素になり得ます。
優れた戦績をおさめても誰かが敷いたレールで結果を出すことは、この先の人生において自ら考えるという力を養わないことになります。
でも当部には良くも悪くもそれがありません。
だからこそ、ここで成し遂げることの方が意味は大きいのです。
青山学院大学という大学はむしろそういう文化であり、環境なんだと私はいつも思っています。
だからこそ今までも自由に、部員たちが自立して、主体性をもって出来るように促してきました。
そしてここから先は、今までの自分を脱皮して、上を目指さないといけないのです。自分の物差しを今こそ捨てるべきなのです。
私たちは決して強豪ではありません。結果を出していない中で、こんな大口を叩けば、何を言っているのかと嘲笑う人もいるかもしれません。
でも私は部員たちが自ら考えて行動し、成果を出してくれるものだと信じています。
それはインカレでメダルを獲るという結果より、もっと大切なことを学べるとすら思っています。
80点でも十分すごいです。そこに到達しない人も多くいるのですから。
でも100点を取るための努力や行動こそが、この先の将来につながっていくことを教えたい。そんな思いでいます。
皆さんは『三木谷曲線』ってご存知ですか。
楽天の三木谷社長の三木谷イズムとは1年365日、毎日の継続を重視しています。
その象徴は『1日1%の改善』です。
どんなことでも毎日1%ずつ改善していくと、1.01の365乗で、1年で37.8倍くらいになります。
それに対して、毎日1%ずつ力を抜いたとすると0.99の365乗で0.026倍。つまり1年で元の実力の40分の1まで下がってしまう計算です。
1年で37倍成長するのと、40分の1まで退化するのと、どっちがいいですか?
昨日より1%だけ上乗せして頑張るというのは、そこまで難易度が高いことではありません。
毎日1%の改善を続けるだけで、誰でも1年で37倍成長できるのであれば、それはもう日本一すら見えてくるかもしれませんね。
でも自分たちだけが成長しているわけではなく、まわりだって同じように成長しているんです。
だから差をつけるためには諦めずに改善し続けることが必要です。
大抵の人は途中でそれを諦め、努力ができなければ改善そのものが止まってしまいます。
しかし、もしこれを諦めずに努力を続けた場合、あるレベルを超えた瞬間に急激に伸びることがあるのです。
そう、これが『三木谷曲線』です。
そしてそこまで努力をし続けた人こそ、勝利という栄光を手にしているのでしょう。
これは一つの例え話です。
でも自分たちが目指すところに辿りにつくにはもうこれしかないのです。
やるかやらないか、すべては自分自身が決めていいことなのですから。
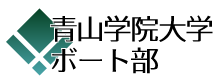



コメント