私事ですが、今月、45歳を迎え、何か新たなことをし始めねばと思い、Instagramを開始ました。
と言ってもアカウントを取得しただけで、まだ活用には至っておりません。。。
そもそもいまだにどういうものかすら理解できていないのですが、登録したからには何かしら活用し始めていきたいとは思っています。
ただ、これはあくまで監督業として活用することを目的としているので、ボートを通じて広がった輪をこれに反映していけたら、なんて思っています。
操作方法すらままならない状態ではあるのですが、部員らに教えてもらいながら、少しでも何かに貢献できたらと思いますので、よろしくお願いします。
さて、本日も週末の振り返りです。
土曜日の試乗会には6名の新入生が参加してくれました。すでに1度は来てくれていた面々でしたので、いよいよボート部の活動開始となるよう、ナックルでの練習を開始しました。
久々に自分も教える側にまわって、コックスをしながら指導しましたが、やはり漕ぎはじめというのは教えるのも、教わる方も難しい競技だなと改めて感じました。
自分ではこうだと分かっていながらも身振り手振りでも中々伝わりません。
そりゃ、何が正解かも分からないまま漕がせているので当然なのですが、今はまだ艇に慣れて、水上で進む感覚を味わってもらうことを主眼としています。
4人が合わせて漕ぐことで、なんとなくでも『息が合ってきた』、少しずつでも『進んできた』というのが、もっともローイングを楽しめている瞬間でもあるでしょうしね。
来月にはいよいよ仮入部として本格的に漕ぎ方なんかも指導していければと思っています。
ボート部が気になってご覧いただいている新入生の皆さん、これからでもまだまだ間に合いますので、是非ご連絡お待ちしております。
そして日曜日には現役部員らの指導に奔走しました。
午前中は1250メニューに自転車で伴走してタイムを計ったり、午後は一緒に乗って教えるなど、どっぷりと練習に時間を費やしました。
現在、陸から見ていてもっとも気になることは、前回でも今後の課題として挙げた『正しいワンストローク』ができていないことでした。
これがなぜかと探求していましたが、実際に一緒に乗ってみるとエントリー動作、キャッチ動作についての理解やそのアプローチが全員違っているなという印象をもちました。
このブログでも何度も触れているようにエントリー動作やキャッチのアクションは実に奥深いです。
ですから午後の乗艇ではまず4人で付きフォアに乗り、白川、淡路のドリルを徹底的に観察しましたが、やはり陸から違和感を覚えたように、エントリーでの戻りが顕著であったこと、そして水のつかみだしが出来ていないことを感じたのです。
基本的に普段のテクニカルドリルではエントリー練習としてチャぼり、キャッチ練習としてつかみを行います。
この練習を教えながら実践しているわけですが、その重要性は理解しつつも、やっている気になっているのも今でした。
ただなんとなく、ではなく、なんのためにやっているか、は大きく違いますよね。
チャボリは上下運動によってエントリーで入水する動きとしては間違いではありません。
でも大きく違うのは、通常の漕ぎ方ではキャッチで止まって、入れる動作を行う暇はありません。
よってチャボリでは入水の感覚は養えますが、これによりキャッチ姿勢に入ってからエントリーするということが無意識に定着しているのを感じました。
またつかみにおいても、ほぼ止まっている艇からつかみを行い、多少は艇が動き、その中で水をとらえます。(要するにどちらかと言うとつかみやすい状態です)
ですが、これもまた普段の漕いでいる状態では、艇はぐんと進み、固定しづらい状況の中で水をつかもうとするので、動作としては一向につながってこないのです。(要するに似て非なる感覚だと言いたいです)
とは言え、ボートのドリルとしてチャボリ、つかみをまず教えます。
でも考えれば考えるほど、案外間違ったことをさせているのではと感じるのです。。。
それこそ新入部員に漕ぎ始めた時の練習として感覚を伝えるのには必要な方法だと思うのですが、これを今の彼らにそのまま当てはめてさせ続けることも違うのかなと感じました。
それは他のドリルでもやはり同じで、腕漕ぎ一つをとっても飯尾に関してはスクウェアではなく、フィニッシュしていたので、あらら・・・と今一度、その目的を理解してもらいました。
そうなると教えるべき点はいくつもありますが、この日に伝えたのは、シートのトップに到達時点で入水するための放り方です。(放り方とはエントリー時の放物線を比喩しています)
そのためには今の最新オールではやはり置いてくるより、積極的に入れに行くと言う表現の方が正しいのでしょうね。
もちろん上下運動や抵抗をなるべく減らし、艇を止めないためには、ソフトさも重要なので、そっと置いてくると私はよく表現します。
でも今の彼らに必要なのは、まず積極的に入れに行くという動作そのものでした。
そのためには、フォワードでのシートスライド後半では準備をしながら狙っていく必要もあるのですが、白川からはその意味が分からないとコメントもありました。
うーん、ますますどう伝えればいいのかと頭を悩ませますが、今はまずシートトップ時点でダイレクトエントリーさせることを最優先させてみようと思うのです。
今までは、より遠くにエントリーしようと伝えてきましたが、これにより無理に突っ込み気味の姿勢を取らせていたことも乗ってみて改めて気づきました。
あくまで自身らの有効レンジを最大限活用していくことが重要で、無理に大きく取りに行くのではなく、決まったレンジの中で、キャッチのための早めの準備行動が大切なんですよね。(これはなんだか普段の生活、行動においても同じです)
ですから、何のためにやっているのか、常に考えて、正解に近づくために探求していくことが、これからは必要なのです。
あとは昨年度購入させていただいたCompブレード、スキニーシャフトの性能は優れものですが、やはり扱うにはそれなりのテクニックを要するのだと感じています。
私なんかは古い道具に慣れてきた人間なので、この最新オールを使いこなせる気がしていません。
特に見ていてもCompブレードの縦幅はやはり長い設計なので、水面ギリギリを狙いに行った際にどうしても弾かれてしまいがちです。
だからこそもっとハンドルを下げて高い位置から放り込んでいいのだとも私は感じています。(どなたか正解が分かれば教えてください笑)
ちなみにこの日の乗艇後半では飯尾とダブルスカルに乗ってあれこれ教えましたが、これもまたうまく伝わらず、、あげく、監督のを見せてくださいと言われ、披露したところ、飯尾自身はそれにより違いを感じるものがあったのか、何かを理解した節がありました。
ただ、理解しつつも、漕いで実践するとなると中々難しい、と言った印象でもあったようですが、見せることが一番の近道でもあるのでしょうね。
そして練習の終わり頃には、教えたことをもとに二人で同じ感覚で漕いでみましたが、初めてと言っていいくらいに私自身はそれこそ自分自身の漕ぎをすることができました。
普段部員らと一緒に乗るときはできるだけ相手に合わせて、バランスを取って漕ぐことを主としていますが、この時は遠慮なく実践させてもらえたので、艇の伸びと漕いでいる際の気持ちよさを普段より感じることもできました。
逆に言えば、飯尾もここまで成長したんだなと実感した瞬間でもあったのですが、動画で改めて見るとキャッチの鋭さはまだまだですが、明らかに先々良くなりそうな印象は受けました。
ここまでの技術を追求して、教えたり、共に考えたりすることも、私自身かつてありませんでしたから、これらを彼らがモノにした時にはこれまでにない成長をきっと遂げることでしょう。
目標のインカレまで残り半年を切りました。課題は山積みでもありますが、まだまだうちのボート部は速くなりそうだと実感した週末でもありました。
新歓もようやく落ち着き、いよいよ自分たちの競技向上に専念できつつある今こそ、更なる成長と進化を遂げるチャンスです。
大いに期待しましょう。
追伸
このブログを読んで先日コメントをくれたT.Kさん。ご無沙汰しております。お互いに今を頑張っていることが分かり嬉しく思いました。またいつか会うその日を楽しみにしております。
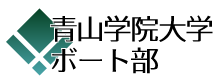


コメント